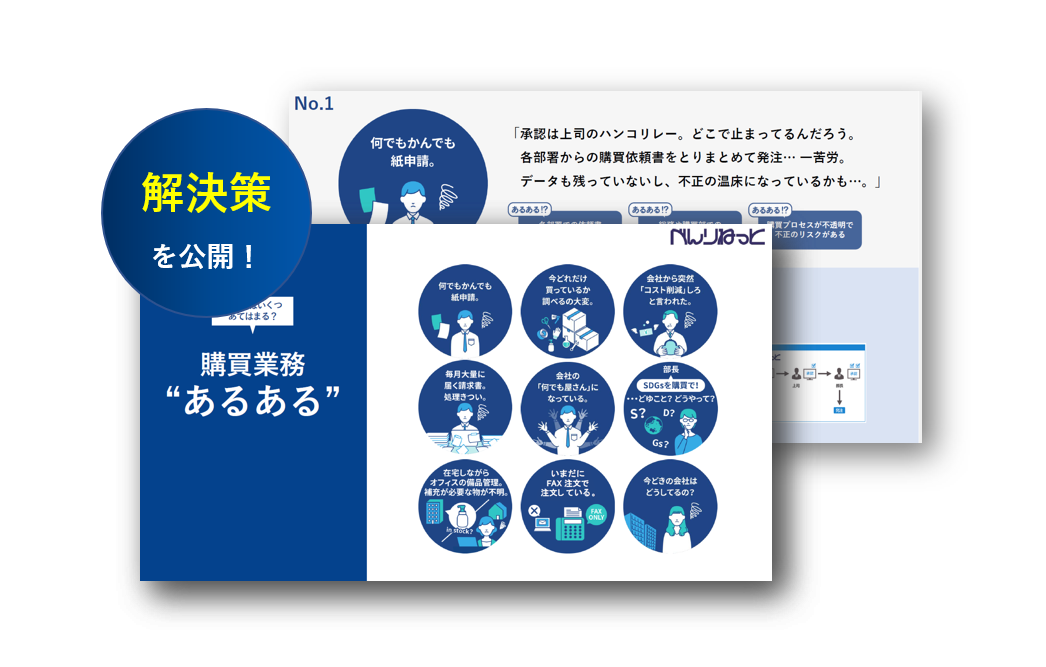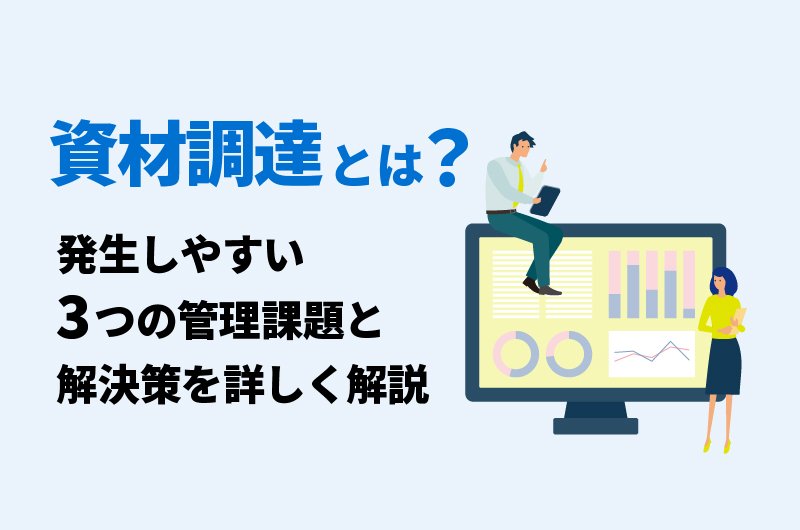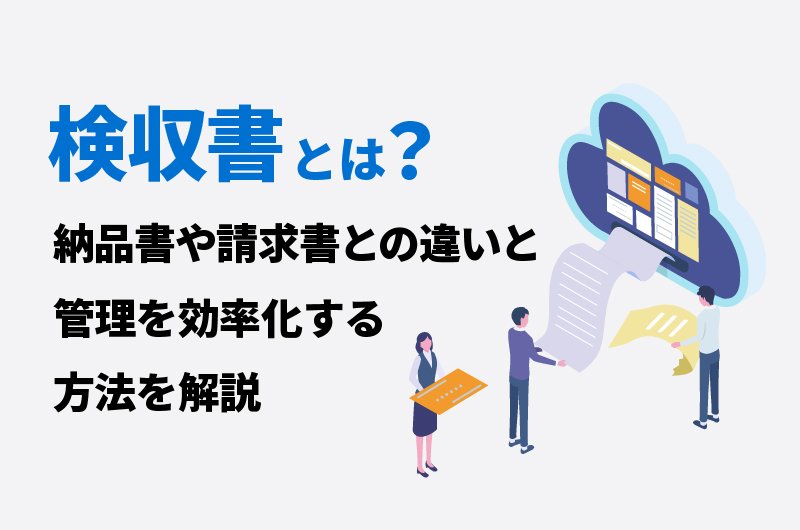RFQ(見積依頼書)とは?RFI・RFPとの違いと効率化の方法を解説

公開日:
RFQ(見積依頼書)は、複数のサプライヤに同じ条件で見積もりを依頼し、公平で効率的な調達を行うための重要な仕組みです。しかし、現場では見積条件が統一されておらず、比較に時間がかかったり、属人的な判断で選定が進んだりと、非効率な状況に悩む企業も少なくありません。
そこで本記事では、RFQ(見積依頼書)の意味やRFI・RFPとの違い、活用するメリットと注意点についてわかりやすく解説します。さらに、購買管理システムを取り入れた具体的な効率化事例も紹介します。
サプライヤ選定に課題を感じている方は、参考にしてみてください。
目次
RFQ(見積依頼書)とは

RFQとは「Request for Quotation」の略で、企業が必要とする商品やサービスを調達する際に、複数のサプライヤに対して同じ条件で見積もりを依頼するための文書です。
RFQでは単に価格を比較するだけでなく、納期や数量・契約条件・製品の仕様なども含めて検討できます。購買担当者はRFQを通じて条件をそろえた見積もりを収集できるため、選定基準が明確になり、判断の公平性と効率性を高められます。とくに、製造業や建設業のように金額規模が大きく、複数の候補から最適な取引先を選定する必要がある業界では、欠かせないプロセスといえるでしょう。
RFQと似た用語との違い

RFQと似ている用語として、以下の2つがあげられます。
- RFI
- RFP
それぞれの用語の違いを明確にし、より戦略的な調達活動を実現しましょう。
RFQとRFI(情報提供依頼書)の違い
RFQとRFIでは、求める情報の具体性に違いがあります。
RFI(Request for Information)は「情報提供依頼書」であり、市場にどのようなサプライヤやサービスが存在するかを幅広く調べるために使用します。購買の条件が固まっていない段階で使用することが多く、各社の技術力や提供範囲、実績などの収集が目的です。情報提供依頼書の回答は、製品カタログやパンフレットなどが該当します。
一方で、RFQは条件が明確になった段階で発行し、価格や納期、数量といった具体的な見積もりを依頼するために使用します。
つまり、RFIで市場の候補を幅広く調査し、その結果をもとにRFQで条件をそろえた見積もりを依頼することで、最終的に取引先となるサプライヤを絞り込むのが一般的な流れです。
RFQとRFP(提案依頼書)の違い
RFQとRFPでは、依頼する対象範囲に違いがあります。
RFP(Request for Proposal)は、サプライヤに具体的な解決策や提案を求める「提案依頼書」です。発注者と受注者の認識をすり合わせ、課題や要件に対して共通の理解をもつことを目的としています。たとえば、ITシステムや大型設備導入のように仕様が複雑で標準化しにくい案件では、単に価格や納期を比較するだけのRFQでは十分に評価できません。RFPを通じて「どう課題を解決するか」「どのような付加価値を提供できるか」といった提案内容も含めて、総合的に検討する必要があります。
つまり、RFQで条件をそろえて候補を絞り込んだうえで、RFPで各社の提案内容を比較・検討して最適なサプライヤを決定するのが一般的な流れです。
サプライヤ選定はRFI・RFQ・RFPの順番で行う

サプライヤ選定は、一般的に以下の3ステップで行います。
| 手順 | 概要 |
| 1.RFI(情報提供依頼書) | 市場にどのようなサプライヤが存在し、どのような製品やサービスを提供できるのかを広く調べる |
| 2.RFQ(見積依頼書) | 必要な数量や仕様、納期などを明示し、複数のサプライヤを客観的に比較できる環境を整える |
| 3.RFP(提案依頼書) | 導入効果や運用方法、付加価値を含めた具体的な提案を受け取り、総合的に評価する |
RFI・RFQ・RFPを順に活用することで、情報収集から見積比較、提案評価までを抜け漏れなく実施でき、自社に最適なパートナーを効率的に見つけられるでしょう。サプライヤの選定や管理については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
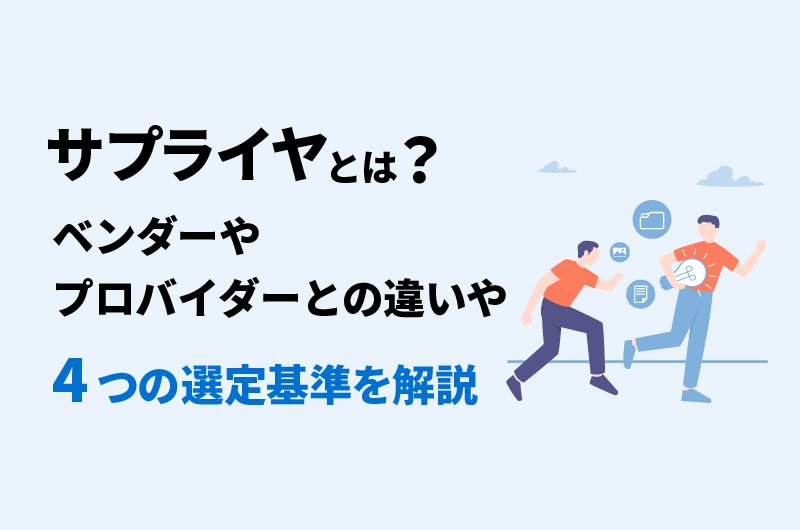
✓ 関連記事もチェック
サプライヤとは?4つの選定基準を解説 >>
ベサプライヤの定義を明確にし、4つの選定基準を解説
RFQを活用して調達を最適化する3つのメリット

RFQを活用するメリットは、主に以下の3つです。
- コスト削減につながる
- 公平で透明性のある選定ができる
- 調達プロセスを効率化できる
サプライヤ選定を最適化したい方は、参考にしてみてください。
コスト削減につながる
複数のサプライヤに対して同じ条件でRFQを提出することで、価格・納期・品質・契約条件などを横並びで比較できます。
条件が統一されていないと「安いと思ったら納期が遅い」「見積もりに含まれていない追加費用が発生する」といったトラブルを招くおそれもありますが、RFQを活用すればこうしたリスクを避けられます。また、競合環境をつくることで、サプライヤ側も適正かつ競争力のある価格を提示しやすくなり、結果的に調達価格の引き下げも期待できるでしょう。
単なる値引き交渉に頼るのではなく、 客観的な比較データにもとづいてコスト削減を実現できる点が、RFQを活用するメリットです。
公平で透明性のある選定ができる
RFQでは、仕様や条件をあらかじめ明示したうえで見積もりを取得するため、どのサプライヤがどのような条件を提示したか明確にわかります。
購買担当者が個々のサプライヤと個別交渉を重ねる方法では、担当者の判断や交渉力に左右されやすく、結果的に「なぜこのサプライヤが選ばれたのか」が不明確になるケースも少なくありません。RFQを活用すれば、選定理由をデータとして明確に示せるため、社内説明や監査対応にも役立ちます。属人的な判断に頼らず、 透明性の高いプロセスで意思決定できることは、組織にとって大きな安心材料となるでしょう。
社内の内部統制に課題を抱いている方は、以下の記事も参考にしてみてください。内部統制が不足することで起こり得るリスクや、強化するための具体的な方法について詳しく解説しています。

✓ 関連記事もチェック
購買プロセスにおける内部統制とは?強化への4ステップを解説 >>
内部統制の重要性や、発生しうるリスク、内部統制を強化する方法を解説
調達プロセスを効率化できる
RFQを活用することで、調達プロセス全体の効率化も期待できます。
サプライヤごとに異なるフォーマットや内容で見積もりが提出される場合、比較や整理に多くの時間と手間がかかってしまいます。RFQを使えば依頼内容を標準化できるため、サプライヤは同じ項目に沿って回答でき、購買担当者も条件を横並びで確認可能です。その結果、 短時間で差異を把握でき、選定までのスピードが格段に上がります。また、情報の抜け漏れや曖昧さが減ることで、後からの確認作業や再依頼の発生を抑えられます。
RFQを作成する際の3つの注意点

RFQは調達の公平性や効率性を高めるうえで有効な手法ですが、作成方法を誤るとかえって手間や混乱を招くことがあります。
RFQを作成する際には、以下の3つに注意する必要があります。
- 条件が曖昧だと正しく比較できない
- ノウハウの属人化は見積もり内容に差が生じる
- 品目が多いと作成・集計の作業が膨大になる
リスクを事前に確認し、確実かつ透明性の高いサプライヤ選定を実現しましょう。
条件が曖昧だと正しく比較できない
RFQを作成する際には、依頼内容と条件をできる限り具体的に記載する必要があります。数量や仕様・納期・納入場所・支払条件などが曖昧なままでは、サプライヤごとに異なる解釈で見積もりが提出され、公平な比較が難しくなるからです。たとえば、同じ製品でも納期が異なれば価格条件も変わるように、条件が統一されていなければ意味のある比較はできません。
依頼条件を明確にすることで、各社が同じ基準で見積もりを提出でき、客観的な判断材料として利用しやすくなります。さらに、不明確な条件による認識のズレや追加費用の発生といったトラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。
ノウハウの属人化は見積もり内容に差が生じる
担当者ごとの判断基準ややり方に差があると、依頼内容の粒度や評価の視点が統一されず、見積もりの品質にばらつきが生じます。担当者が退職や異動をした際にノウハウが引き継がれず、業務の停滞や品質低下につながるおそれもあるでしょう。
本来のRFQは、誰が担当しても一定の水準で作成できるよう、条件や評価基準を明文化して組織で共有するべきです。属人的な運用を放置すると、調達の透明性や公平性を損なうおそれがあります。RFQを機能させるためには、知識やノウハウを個人にとどめるのではなく、標準化と仕組み化を徹底して、組織として一貫した調達力を維持できる体制を築くことが重要です。
品目が多いと作成・集計の作業が膨大になる
RFQは、少数の品目であれば比較的容易に運用できますが、扱う品目数が増えると作成や集計の作業が膨大になります。依頼書の記載項目が多いほど入力や確認の負担が増え、サプライヤ側も回答に時間を要するため、全体の進行が遅れやすくなるでしょう。さらに、提出された大量の見積もりを整理して比較する作業も手作業では非効率になり、入力ミスや集計漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。とくに品目数の多い間接材の見積もり比較は、RFQの管理そのものが担当者にとって大きな負担となりかねません。
効率的に運用するためには、回答形式を統一したり、管理を一元化できる仕組みを取り入れたりする工夫が必要です。
見積もり依頼を効率化するなら「購買管理システム」がおすすめ

従来のようにメールやExcelで複数のサプライヤとやり取りしていると、回答内容の整理や比較に手間がかかり、進捗管理も煩雑になります。とくに品目や発注頻度の多い間接材では、都度見積もりを取ったり、複数の部署から同じような内容の見積もりを取ったりするのは非効率です。
そこで有効なのが、購買管理システムの導入です。
まとめて取得した見積もり結果をシステムに品番登録し、全社で同一条件の発注ができる仕組みを整えることで、重複をなくして無駄のない購買を実現できます。
また、見積商談をシステムにより電子化することで、進捗状況や履歴も一元的に管理できるようになり、透明性と再現性が向上します。これにより、属人的な判断に依存しない、客観的で公平な調達プロセスを構築可能です。複数サプライヤへの見積依頼、採用・不採用連絡も一斉に自動で送付できるため、コミュニケーションにかかる工数も削減できるでしょう。
購買管理システムを活用することで、コスト削減だけでなく業務のスピードと正確性を同時に実現できます。以下の記事では、購買管理システムで実現できることや選定する際のポイントについて詳しく解説しています。

✓ 関連記事もチェック
購買管理システムとは?便利な機能や導入メリットを解説 >>
購買管理システムの機能やメリット、システムの選び方を解説
間接材の購買管理システムである「べんりねっと」でできることや、導入の流れを知りたい方は、以下の資料をお役立てください。

✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
べんりねっとサービス紹介資料 >>
「べんりねっと」でできることを一つにまとめました
購買管理システムが見積もり依頼の業務改善につながった事例3選

購買管理システムが見積もり依頼の業務改善につながった事例を、3つご紹介します。
- 見積もり商談機能で購買支出を約1割削減
- 「相見積もり不要」の仕組みづくりで発注工数が約50%削減
- 購買業務効率化によって相見積もりの徹底が実現
自社の現状と照らし合わせ、購買管理システムの導入を検討してみてください。システム導入による成功事例については、以下の資料でも詳しく解説しています。

✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
~成功事例から学ぶ~間接材の購買業務 改善手法 >>
間接材購買の改善手法と成功事例をご紹介
見積もり商談機能で購買支出を約1割削減
総合建材メーカーの「三協立山株式会社」では、べんりねっとでサプライヤの競争環境を整えたことで、購買支出の約1割を削減しています。
同社では、新規購入や一定期間を空けた再購入の際に、必ず2社以上から相見積もりを取得するルールを設けていました。しかし、繁忙期や担当者のリソースが限られる状況では、そのルールの徹底が難しいという課題がありました。べんりねっと導入後は、サプライヤへの相見積もりや、比較選定・候補先への採用・不採用通知などの業務がすべてシステム上で完結し、業務負担を大幅に削減できています。サプライヤ選定に関する業務が減ったことで、相見積もりに関する社内ルールも徹底できるようになりました。
本事例については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「三協立山株式会社」様 >>
工場ごとに分散していた購買先を集約して相見積もりの徹底を実現
「相見積もり不要」の仕組みづくりで発注工数が約50%削減
食品製造業の「カルビー株式会社」では、べんりねっとで見積もり比較や価格比較などを含む購買業務を効率化し、発注工数の約50%を削減できています。
同社では、すべての購買品について2社以上から相見積もりを取るルールを設けていましたが、工場ごとに購買単価が異なり、その基準も不明確な状態でした。「べんりねっと」導入後は、購買部門が交渉した単価をシステム上に登録し、全拠点で共有しました。これにより、各工場が個別に相見積もりを行う必要がなくなり、業務負担を大幅に軽減できています。また、外部サイト連携先のカタログを横断的に一括で検索できる「サイト間一括検索機能」の活用で、商品の比較時間が1/10まで短縮しました。システムに単価を集約したことで、拠点ごとのばらつきがなくなり、調達の透明性とルールの徹底が実現しています。
本事例では、業務効率のほかに、発注者の約6割がコストの削減も実感しています。購買業務の工数やコストに課題を感じている方は、参考にしてみてください。
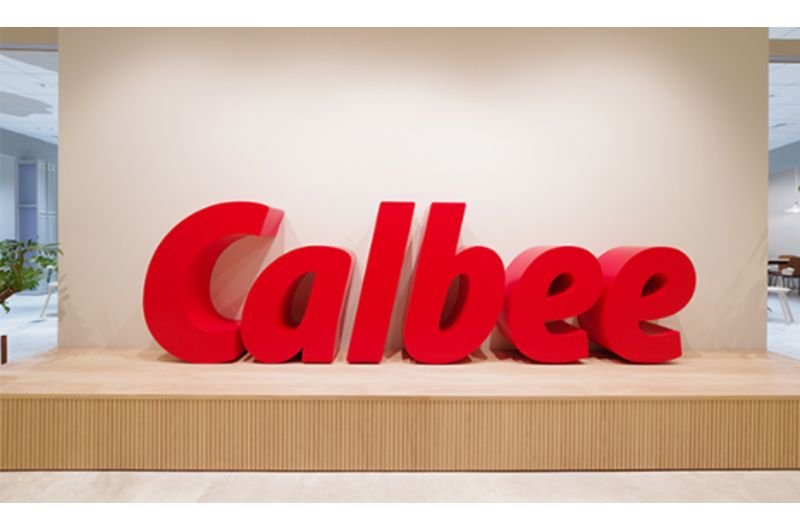
✓ 導入事例をチェック
「カルビー株式会社」様 >>
発注工数の約50%を削減し、約6割の発注者がコスト削減を実感
購買業務効率化によって相見積もりの徹底が実現
医薬品製造業の「太陽ファルマティック株式会社」では、べんりねっとの導入により購買業務を一元管理できるようになり、社内ルールとして定めていた相見積もりの徹底運用を実現しています。
従来は3つの購買管理システムを併用し、200社におよぶサプライヤと個別でやり取りしていました。Excelで発注書を作成していたため、情報が分散し管理に限界を感じていたといいます。そこで、べんりねっとに一本化して購買データを集約したことで、従来の請求書払いを「支払通知方式」への切り替えに成功しました。これによって、発注から会計処理までのトータル時間を約65%削減しました。効率化で生まれた時間を活用し、定番商品の再見積もりや購買分析、ボリュームディスカウントの交渉など、コスト削減に向けた活動にも着手できています。
本事例について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「太陽ファルマテック株式会社」様 >>
発注から会計処理までのトータル時間を約65%削減
RFQを最適化して戦略的な調達活動を実現しよう

RFQ(見積依頼書)は、公平で効率的なサプライヤ選定を行うための重要な仕組みです。適切に運用すれば、コスト削減や内部統制の強化、意思決定の透明性向上にもつながります。一方で、条件が曖昧だったり、品目が多すぎたりすると、見積比較や集計に時間がかかり、調達のスピードや精度が低下しかねません。
こうした課題を解決するには、RFQのプロセスを標準化・電子化することが不可欠です。
間接材の購買管理システム「べんりねっと」を活用すれば、見積依頼から集計・選定までを一元管理でき、業務効率とコスト削減を同時に実現できます。
RFQのプロセスを効率化し、調達の最適化と企業の競争力向上を実現しましょう。