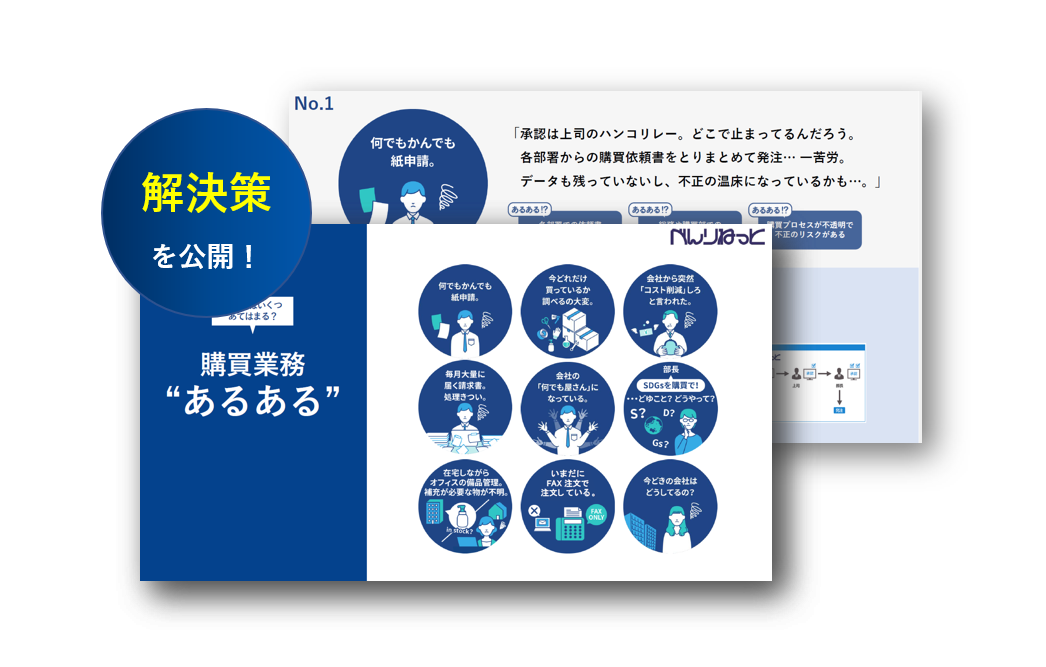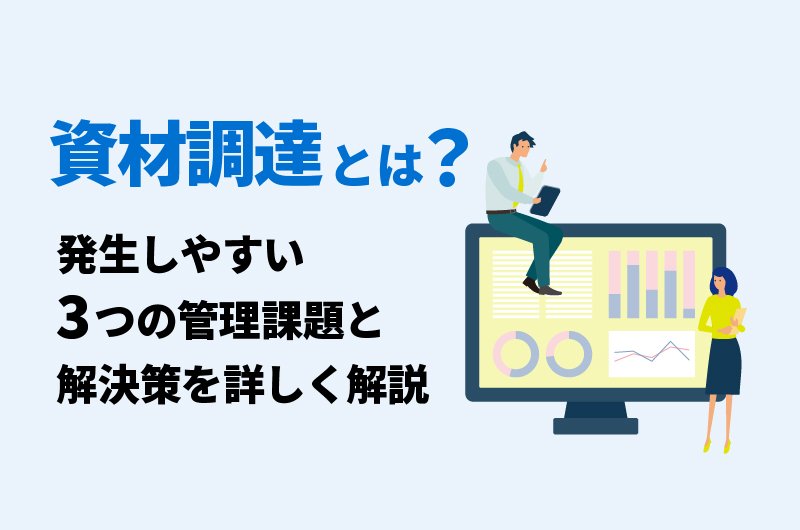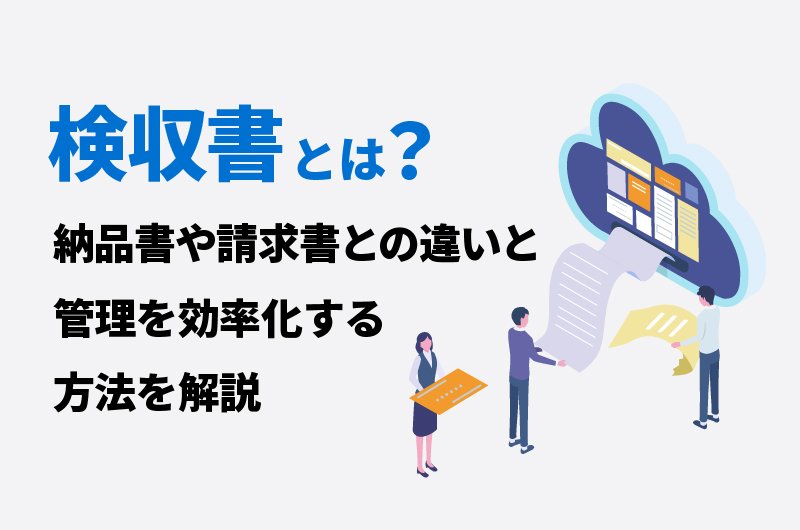企業の消耗品管理とは?備品や雑費との違いや5つの課題と解決方法を解説
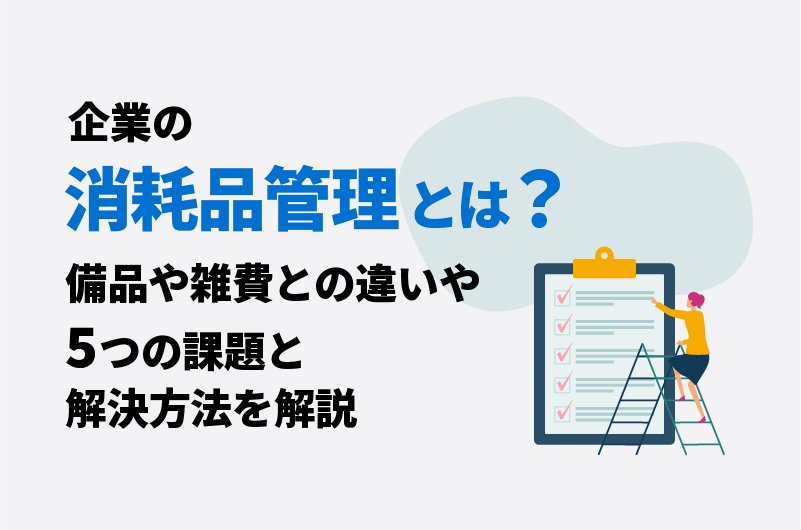
公開日:
企業における、コピー用紙や文房具、清掃用品などの「消耗品」は、日々の業務に欠かせない存在です。しかし管理が不十分だと、在庫切れや二重発注、経費計上漏れなどの課題が積み重なり、気づかないうちに無駄なコストが発生してしまいます。
いま企業に求められているのは、消耗品を単に安く購入することではなく、いかに効率的かつ正確に管理して無駄をなくすかという視点です。
本記事では、消耗品の定義や勘定科目上の位置づけ、管理が難しい理由とその解決策を紹介します。自社の消耗品管理に課題を感じている方は、参考にしてみてください。
目次
消耗品とは?定義と具体例

経理の分野でいう消耗品とは、使用頻度が高く、短いサイクルでの消費を前提とした物品を意味します。資産のように長期的に保有するものではなく、日々の活動を支えるために繰り返し購入するものです。英語では「supplies」「consumables」などと表現され、会計上では「Supplies Expense」と記載することもあります。
消耗品の例として、以下があげられます。
| 区分 | 具体例 |
| 事務用品 | コピー用紙・ノート・付箋・封筒・ペン |
| OA関連 | プリンターインク・トナー・USBメモリ・LANケーブル |
| 清掃・衛生用品 | トイレットペーパー・ティッシュ・洗剤・消毒液・ゴミ袋 |
| 工場・現場用品 | 作業手袋・マスク・養生テープ・潤滑油・工具の替刃 |
| 接客・応接用品 | 来客用お茶・コーヒー・紙コップ・紙皿 |
| 物流・梱包用品 | 段ボール・緩衝材・包装用テープ・ラベルシール |
消耗品は一つひとつの金額が小さいため軽視されやすいですが、継続的に発生する支出であることから、積み重なると大きなコストになります。
消耗品を含む間接材の管理について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください
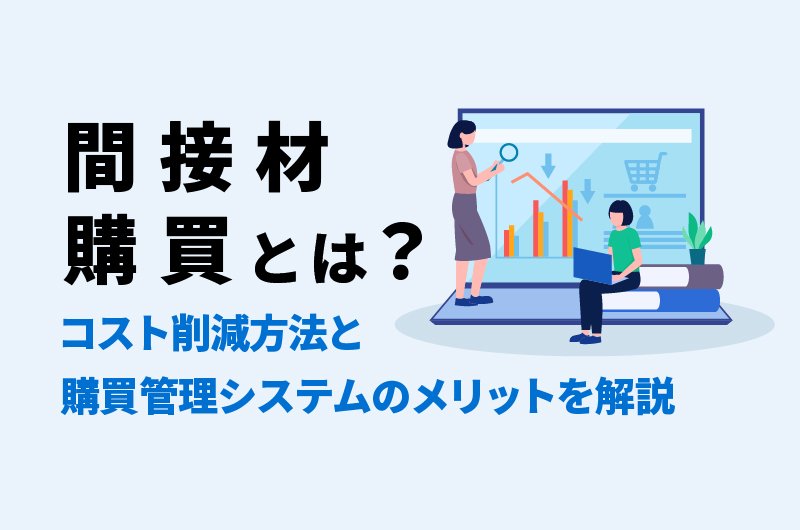
✓ 関連記事もチェック
間接材購買とは?コスト削減方法と購買管理システムのメリットを解説 >>
間接材購買における6つの特徴とコストを削減する方法を解説。
消耗品費の勘定科目での扱い
短期間で使い切る消耗品の購入費は、「消耗品費」という勘定科目で処理します。
国税庁によると、消耗品費は「使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」と定義されています。金額が小さいまたは耐用年数が短い品目は、資産計上ではなくその年度の費用として処理できるという考え方です。
ただし、中小企業や個人事業主であれば、10万円以上でも取得価額が30万円未満の資産は、少額減価償却資産の特例を用いて一括で経費にできる場合もあります。消耗品費は一見シンプルな科目に思えますが、金額や使用期間によって判断が分かれるため、正しい基準を理解して仕訳する必要があります。
消耗品と区別が必要な科目

消耗品費と混同しやすい科目は、以下の2つです。
- 備品(資産)
- 雑費
似た科目との違いを理解し、消耗品費の会計処理を正しく行いましょう。
消耗品費と備品(資産)の違い
消耗品と備品(資産)の違いは、使用期間と金額の基準です。消耗品は短期間で使い切る物品で、主にコピー用紙やペン、インクなどです。
一方で備品は、正式には「工具器具備品」という資産科目を指し、机・椅子・パソコン・複合機など、長期間使用できる物品を指します。
国税庁の基準では、「使用可能期間が1年以上かつ取得価額が10万円以上」であれば工具器具備品に該当し、減価償却によって複数年にわたり経費計上します。ここでいう取得価額は、本体代金だけでなく設置や工事にかかる費用も含まれる点に注意が必要です。たとえばコピー機を購入する場合、本体価格が9万円でも搬入や設置費用をあわせて10万円を超えると備品として扱われます。
実務では「備品」という言葉が広く使われますが、会計上は資産として扱うか、消耗品費として費用計上するかの判断が重要です。
消耗品費と雑費の違い
消耗品費と雑費はどちらも費用科目ですが、用途と位置づけが異なります。
消耗品費はコピー用紙や文房具など日常的に使う物品に充てられるのに対し、雑費は他の科目に分類できない少額かつ一時的な支出を処理するための科目です。
雑費の例として、以下があげられます。
- ごみの処分代
- 役所での証明書発行手数料
- 一時的な物品のレンタル費用
- 少額の寄付金や協賛金
雑費は、あくまで他の科目にあてはまらない支出を処理するための科目です。消耗品費など該当する科目がある場合はそちらを使い、雑費に計上する際は摘要欄に内容を明記して内訳が不透明にならないよう注意しましょう。
消耗品管理における5つの課題

消耗品は日々の業務に欠かせない一方で、金額が小さいからこそ管理が後回しになりやすく、思わぬコストや業務負担を生むことがあります。
消耗品管理において企業が直面しやすい課題は、主に以下の5つです。
- 在庫状況を正確に把握しにくい
- 発注の重複や過剰購入が発生しやすい
- 経費処理が煩雑で計上漏れが発生しやすい
- コストの全体像が見えにくい
- 不正が起きやすい
自社の消耗品管理であてはまる項目がないか、一度チェックしてみてください。
また、以下の資料では、消耗品をはじめとする間接材の管理不足によって生じるリスクを詳しく解説しています。間接材購買の適正な管理体制づくりにお役立てください。
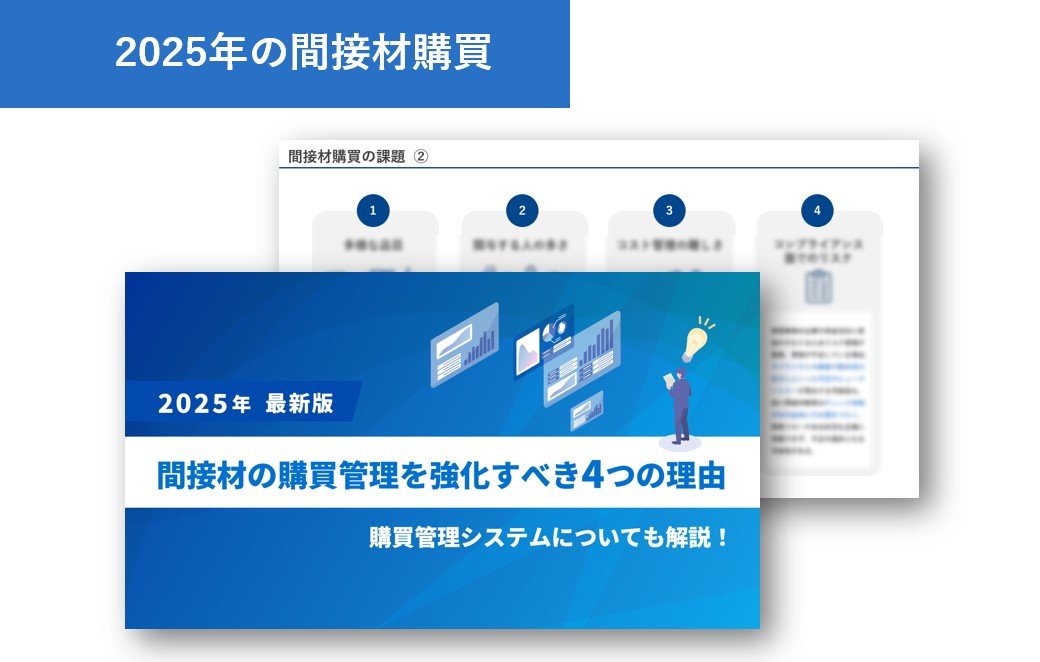
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
間接材の購買管理を強化すべき4つの理由 >>
間接材購買ので起こりうるリスクと今必要な対応を解説。
在庫状況を正確に把握しにくい
消耗品は日常的に使うため使用ペースが一定ではなく、気づいたときには不足していたというケースも少なくありません。とくに複数の部署や拠点で同じ消耗品を利用している場合、各担当者がそれぞれ管理していると、全体の在庫数を正確に把握することは困難です。
在庫確認を定期的に行っていなかったり、Excelや紙ベースの管理台帳を更新しないまま放置することで、実際の在庫と記録にズレが生じることもあります。その結果、必要なときに在庫が切れて業務に支障が出たり、余分に仕入れて保管スペースを圧迫したりするなど、管理不備による無駄が発生しやすくなります。
発注の重複や過剰購入が発生しやすい
消耗品は使用頻度が高いため、必要になった時点で都度購入するケースが多く、発注の重複や過剰購入が起こりやすくなります。たとえば同じ部署で担当者が複数いると、それぞれが在庫を十分に確認せず発注してしまい、同じ物品が二重に届くこともあります。
また、発注のルールが統一されていない企業では、部署ごとに異なるタイミングや仕入先で発注してしまうため、コストが膨らみやすくなるでしょう。割高な単品購入を繰り返すことによって、まとめ買いによるコスト削減のチャンスを逃してしまうおそれもあります。
一つひとつは小さな金額でも、積み重なれば大きな無駄となるため、発注の重複や過剰購入は軽視できない課題といえます。
経費処理が煩雑で計上漏れが発生しやすい
消耗品の購入は少額で回数が多い傾向があるため、経費処理が煩雑になりやすい点も実務上の大きな課題です。
領収書や請求書の数が膨大になり、整理や入力に時間がかかるだけでなく、担当者が処理を後回しにして計上漏れが発生するおそれもあります。消耗品費と備品費、雑費との区別に迷い、誤った勘定科目で仕訳してしまうケースもあるでしょう。その結果、決算時に修正が必要になったり、経理データの信頼性が損なわれたりするリスクもあります。
消耗品は頻繁に発生するからこそ計上漏れや誤分類のリスクが高く、経理担当者の負担が大きくなる分野です。
コストの全体像が見えにくい
消耗品を部署ごとにバラバラに購入していると、全体でどれだけの費用がかかっているのか把握しにくくなり、経営層が正確な判断を下せなくなることもあります。また、個別発注が積み重なると、仕入先との価格交渉やまとめ買いによるコスト削減の機会を逃してしまいます。
消耗品は「少額だから管理不要」と思われやすいですが、年間を通じて集計すると相当な支出になることも珍しくありません。コストの全体像を見える化できていないことは、経営資源の最適配分を妨げる大きな要因となるため、管理の見直しが必要です。
消耗品を含む間接材のコストに課題を感じている方は、以下の資料も参考にしてみてください
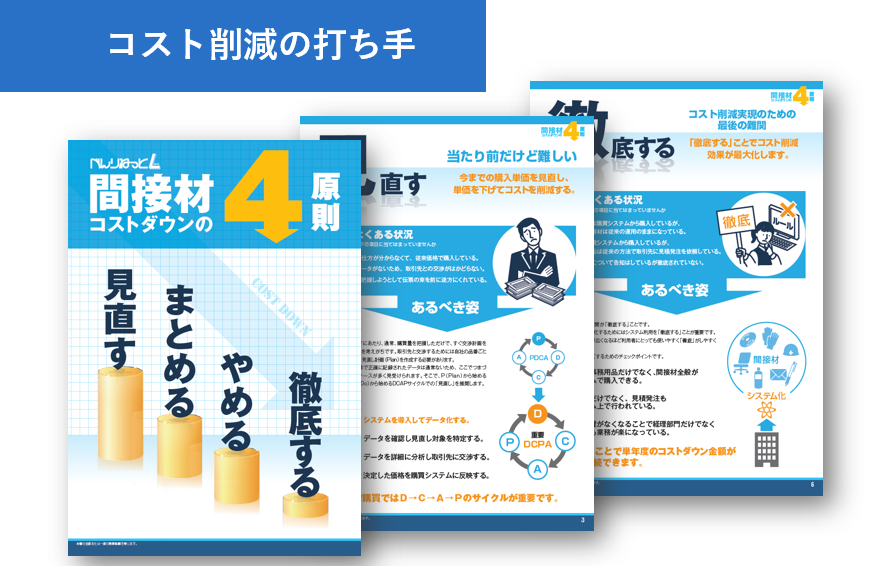
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
間接材コストダウンの4原則 >>
コストダウンの4原則と取り組み方を解説。
不正が起きやすい
消耗品は、金額が小さいため承認が形だけのものになりやすく、不正利用や私的流用が発生しても気づきにくいというリスクがあります。たとえば、個人利用のために日用品を購入して業務用として計上したり、必要以上に発注して横流ししたりするケースです。
在庫や利用状況を細かくチェックする仕組みが整っていなければ、こうした不正を長期間にわたって見過ごすおそれがあります。
少額だからこそ監視の目が行き届きにくく、不正が積み重なることで予想以上の損失につながりかねません。自社の購買プロセスにおける内部統制に課題を感じている方は、以下の記事も一度チェックしてみてください。

✓ 関連記事もチェック
購買プロセスにおける内部統制とは?強化への4ステップを解説 >>
購買プロセスにおける内部統制の重要性や、発生しうるリスクを解説。
消耗品管理の課題を解決するなら購買管理システム

消耗品は金額が小さいからこそ承認が形だけのものになりやすく、発注の重複や過剰購入、経費計上漏れなどが発生しやすい領域です。
エクセルや紙ベースでの管理では、処理の抜け漏れや情報の分散が起こりやすく、経理担当者の負担も増えてしまいます。
こうした課題を解消するためには、購買管理システムの導入が有効です。購買管理システムを活用すれば、発注から承認・納品・検収までの流れを一元管理でき、購買データも見える化できます。無駄な発注や計上漏れを防げるだけでなく、不正利用の抑止にもつながるでしょう。
消耗品は少額の積み重ねで大きなコストになるため、効率的かつ透明性の高い仕組みを整えることが重要です。
買管理システムで実現できることを具体的に知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

✓ 関連記事もチェック
購買管理システムとは?便利な機能や導入メリットを解説 >>
購買管理システムの機能やメリットを解説。
購買管理システム「べんりねっと」が消耗品管理に選ばれる3つの理由

べんりねっとが消耗品を含む間接材購買の効率化に選ばれる理由は、以下の3つです。
- 発注を最適化して無駄なコストを削減
- 発注から検収までを一元化管理して業務を効率化
- 購買データを見える化して不正を防止
日々の消耗品管理における無駄やリスクに課題を感じている方は、参考にしてみてください。
発注を最適化して無駄なコストを削減
購買管理システム「べんりねっと」を導入すれば、全社を通して購買フローを統一でき、結果として購入先の集約や購買データの一元化が可能となります。消耗品管理でよく起こる課題のひとつが、各拠点・部署ごとに仕入れ先や商品価格がバラバラになり、無駄が発生することです。
べんりねっとなら全社で発注を一元化できるため、ボリュームメリットや購買データをいかしたコストダウンを図ることができます。
以下の記事ではべんりねっとの導入で発注者の約6割が10%以上のコスト削減を実現した事例を紹介しています。購買プロセスに負担を感じている方は、一度チェックしてみてください。
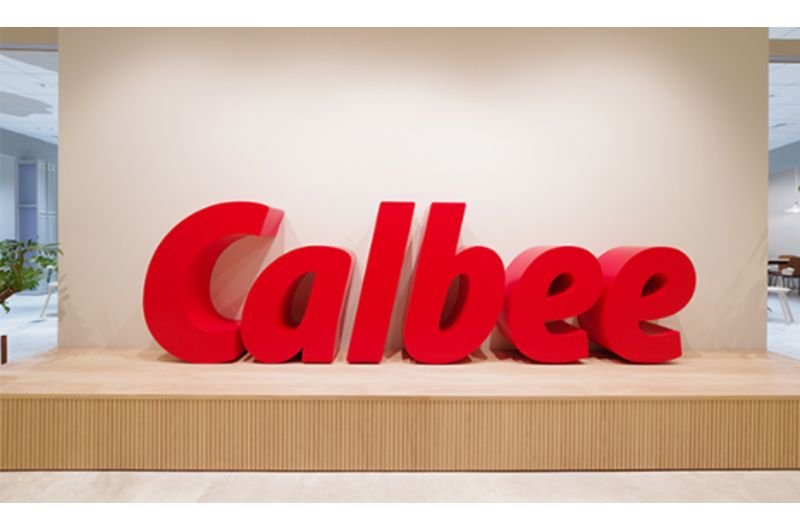
✓ 導入事例をチェック
「カルビー株式会社」様 >>
べんりねっとへの集約で発注工数とコストの削減を実現
発注から検収までを一元化管理して業務を効率化
べんりねっとを導入すれば、発注依頼から承認・納品・検収までの流れをシステム上で一元管理できるため、購買プロセス全体をスムーズに進められます。消耗品の購買プロセスは複数のステップを経るため、紙やエクセルに依存した管理では煩雑になりがちでした。しかしべんりねっとなら、承認フローがオンラインで完結するため、外出中でも即時対応でき、発注リードタイムを短縮できます。
さらに、社内の会計システムと連携することで、仕訳や計上漏れのリスクを軽減し、経理担当者の負担も大幅に削減可能です。
以下の記事では、200社の既存サプライヤをべんりねっとに集約し、業務時間を大幅に削減した事例を紹介しています。取り扱う品目やサプライヤの多さに課題を感じている方は、参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「太陽ファルマテック株式会社」様 >>
自社システムとの連携で発注から会計処理までの業務時間を約65%削減
購買データを見える化して不正を防止
べんりねっとでは、すべての購買データがシステム上に記録されるため、発注から承認・納品・検収までの履歴を一目で確認できます。
従来の紙やエクセル管理では履歴が分散し、誰がいつ何を発注したのか追跡が難しく、不正や私的利用が紛れ込みやすい点が課題でした。
しかし、べんりねっとなら不自然な発注や利用実態との乖離を早期に発見でき、不正の抑止力として機能します。さらに、購買データが蓄積することで、監査時にも透明性の高い記録を提示でき、内部統制の強化にもつながるでしょう。
以下の資料では、社内経費総額の75%をべんりねっとに集約して、購買ルールを徹底した事例について紹介しています。社内の内部統制に課題を感じている方は、参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「ソレキア株式会社」様 >>
べんりねっとによる購買ルールの徹底で内部統制を強化
無駄を省いた消耗品管理で企業の生産性を高めよう

消耗品管理は、日々のコストを抑えるだけでなく、業務の透明性を高め、内部統制を強化するうえでも必要な取り組みです。
発注から承認・納品・検収までの一連の流れを標準化し、データで見える化することで、重複発注や計上漏れ、不正の早期発見につながります。
従来の紙やエクセル中心の運用では限界があるため、標準化とシステム化を組み合わせて実務に落とし込むことが大切です。
購買管理システム「べんりねっと」を導入すれば、購買プロセスを一元管理しながら、コスト削減・内部統制の強化・業務効率化を同時に実現できます。まずは現状の購買フローや支出を見える化し、優先度の高い領域から段階的に仕組み化を進めていきましょう。