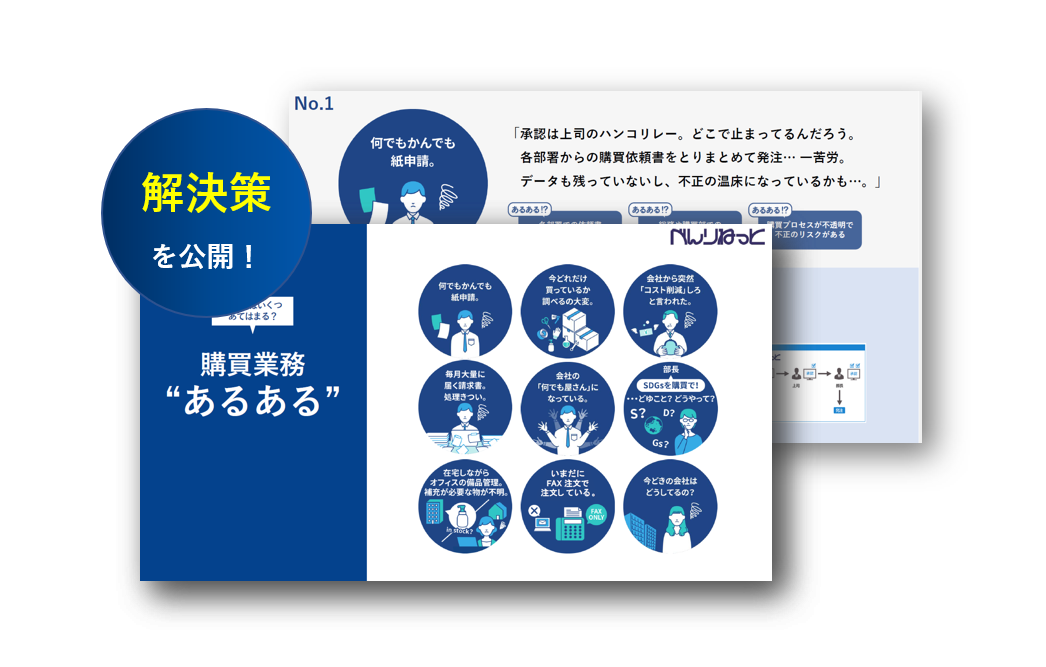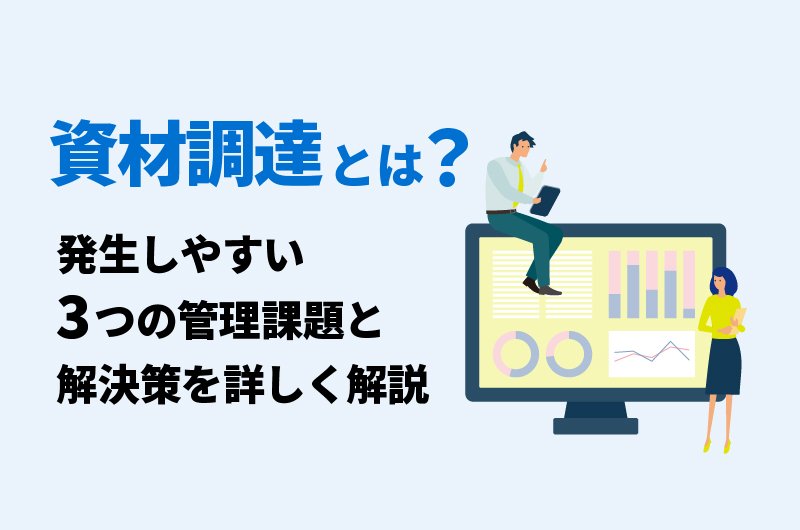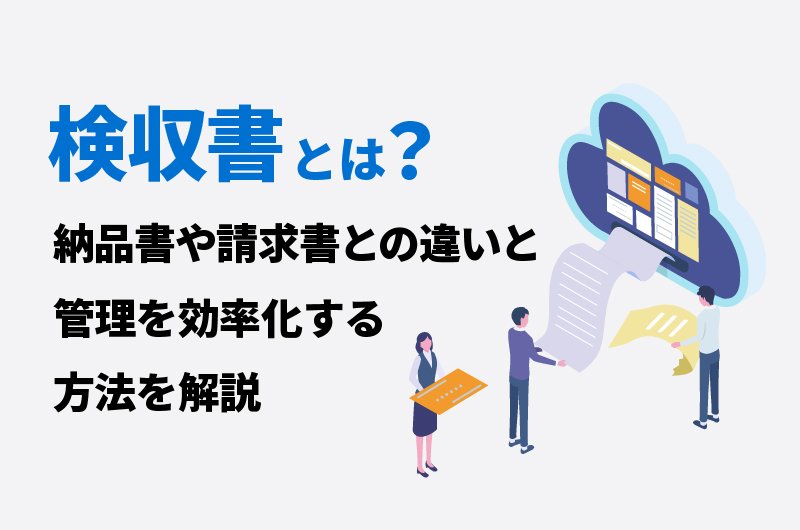バリューチェーンとは? 分析のやり方から実務活用事例までわかりやすく解説
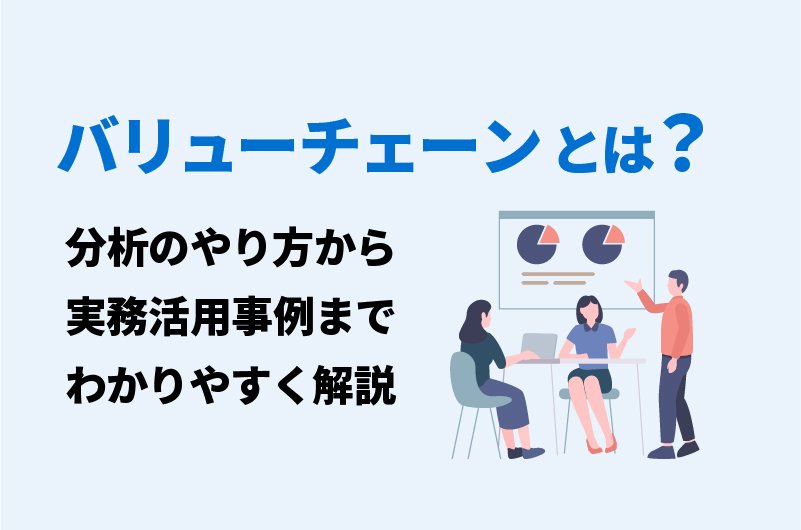
公開日:
企業に求められる市場での優位性は、単に安くモノを仕入れて売ることではなく、付加価値をいかに高めて顧客へ届けるかという点に移り変わっています。その基盤として注目されているのが「バリューチェーン」です。バリューチェーンの分析を通じて強みと弱みを明確化することで、市場での競争力向上につながります。
本記事では、バリューチェーンの定義や構造、分析する4つのステップについて詳しく解説します。自社の取り組みに課題を感じている方は、参考にしてみてください。
目次
バリューチェーンとは?

バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを生み出し、顧客に届けるまでの一連の活動を「価値の流れ」としてとらえる考え方です。アメリカの経営学者マイケル・ポーターが提唱したフレームワークで、単なる業務のつながりではなく、各段階でどのように付加価値を生み出せるかを明らかにすることを目的としています。
たとえば、原材料の調達から製造・物流・販売・アフターサービスまでの流れを分解し、それぞれが顧客満足や企業収益にどう結びつくかを分析します。
この視点をもつことで、自社の強みや弱みを可視化でき、無駄の削減や効率化を進めやすくなるのです。つまり、バリューチェーンは自社の活動を整理し、競争優位につなげるための基盤といえます。
バリューチェーンと似た用語との違い

バリューチェーンと似た用語として、以下があげられます。
- サプライチェーン
- エンジニアリングチェーン
- 調達・購買
違いを理解することで自社の強化すべき領域が明確になり、競争力強化や収益向上といった具体的な成果につなげやすくなるでしょう。
バリューチェーンとサプライチェーンの違い
バリューチェーンとサプライチェーンには、焦点を当てる対象に違いがあります。
サプライチェーンは、原材料の調達から製造・物流・販売までのモノの流れを管理する仕組みです。商品を効率よく顧客に届けることが目的であり、コスト削減や在庫管理の最適化が重視されます。
一方でバリューチェーンは、単に物流を管理するのではなく、その過程で「どのように付加価値を生み出すか」に注目する点が特徴です。
サプライチェーンが「モノの流れを効率化する仕組み」だとすれば、バリューチェーンは「流れ全体を通じて価値を創出する視点」であるといえます。
バリューチェーンとエンジニアリングチェーンの違い
バリューチェーンとエンジニアリングチェーンには、価値を生み出す過程における範囲の違いがあります。
エンジニアリングチェーンとは、製品の企画構想から設計・開発・生産準備・アフターサービスまでの「設計情報の流れ」を指します。技術的な情報や設計データの連携を通じて、開発効率や品質向上を図る仕組みです。
一方でバリューチェーンは、企画や開発にとどまらず、調達から生産・販売・サービスまでを含めた全体の流れをとらえ、そのなかで価値を最大化する視点をもちます。
つまり、エンジニアリングチェーンはバリューチェーンの一部を構成する要素であり、設計工程の効率化を担うことで、企業価値の向上に貢献します。
バリューチェーンと調達・購買の違い
バリューチェーンと調達・購買は、扱う範囲に違いがあります。
調達や購買は、製品やサービスを作るために必要な原材料や部品を、外部から仕入れるプロセスを指します。価格交渉や取引先の選定、納期管理などが中心的な業務となり、いかに低コストで安定的に資材を確保するかが重要です。
一方バリューチェーンは、調達・購買も含めて製品が顧客に届くまでの全体の流れをとらえ、そのなかでどのように付加価値を高めるかを考えます。たとえば、単に安く仕入れるだけでなく、持続可能な調達を行うことでブランド価値を高めたり、購買データを分析して全体最適につなげたりするのもバリューチェーンの視点です。
調達・購買はバリューチェーンの一部であり、単にコスト削減だけでなく、全体の企業価値向上につながる視点で取り組むことが求められます。企業における購買プロセスや適正化の方法については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
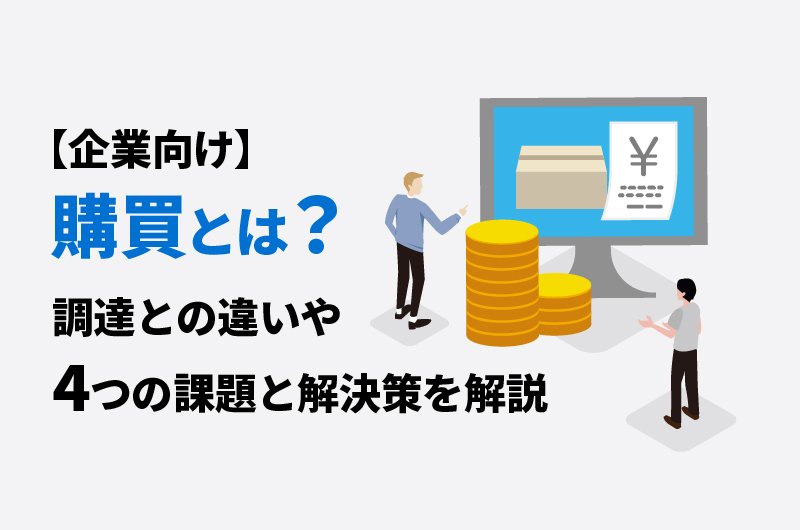
✓ 関連記事もチェック
【企業向け】購買とは?調達との違いや4つの課題と解決策を解説 >>
購買業務の基本プロセスや発生しやすい4つの課題を解説。
バリューチェーンの構造

バリューチェーンは、大きく以下の2つにわけられます。
- 主活動
- 支援活動
2つの関係を正しく理解し、自社の強化できるポイントをより明確にしましょう。
主活動|付加価値を生む主要プロセス
バリューチェーンにおける主活動とは、製品やサービスが顧客に届くまでの流れのなかで、直接的に価値を生み出すプロセスを指します。
代表的な5つの主活動は、以下の通りです。
| 活動名 | 概要 |
| 購買物流 |
|
| 製造 |
|
| 出荷物流 |
|
|
販売・ |
|
| サービス |
|
主活動は連続した工程であり、どの段階でも顧客の満足度に直結する付加価値が生まれます。たとえば、効率的な購買プロセスは余分なコストを削減し、適切な調達先の選定は品質の安定や取引先との信頼関係構築につながります。
主活動は「顧客に価値を届ける道筋そのもの」であり、バリューチェーンの中心的役割を担っているのです。
支援活動|主活動を支える基盤
支援活動は、主活動の基盤を支える重要な役割を果たします。
代表的な4つの支援活動は、以下の通りです。
| 活動名 | 概要 |
| 全般管理 |
|
| 人事・労務管理 |
|
| 技術開発 |
|
| 調達 |
|
バリューチェーン分析のやり方

バリューチェーン分析を効果的に行うためには、感覚や経験に頼るのではなく、体系的なステップを踏んで進めることが大切です。
バリューチェーン分析の進め方は、以下の4ステップです。
- 図やテンプレートを活用して事業活動を洗い出す
- コストと価値を把握する
- 自社の強み・弱みを特定する
- VRIO分析を実施する
効果的なバリューチェーン分析を実施することで、データに基づいた経営判断が可能になります。
ステップ1.図やテンプレートを活用して事業活動を洗い出す
バリューチェーン分析をはじめるには、まず自社の事業活動を主活動と支援活動にわけて整理しましょう。
事業活動を洗い出すことで、自社が競争上どの領域に強みがあり、どこに課題があるのかを把握できるようになるのです。
また、部門や部署ごとの業務フローをすべて可視化することで、顧客への価値提供に直結するプロセスを特定できるようになります。図やテンプレートを使って整理することで、複雑な業務の関係性が一目でわかるようになります。
ステップ2.コストと価値を把握する
事業活動を洗い出したら、それぞれのプロセスにどれだけコストがかかり、どの程度の価値を生み出しているかを把握します。
たとえば、以下のようなコストを明確化します。
- 仕入先ごとの単価や発注にかかる手数料
- 納期遅延による追加コスト
- 在庫をもちすぎた際の保管費用
一方で、その活動が顧客にどのような価値を提供しているかも評価しましょう。高コストでも高い付加価値を生み出していれば強みに、コストが高いのに価値が低ければ改善の余地があると判断できます。
ステップ3.自社の強み・弱みを特定する
コストと価値を整理したら、競合他社と比較しながら自社の強みと弱みを特定します。
データの分析に加えて、購買や製造など現場担当者の声を取り入れることも大切です。現場の意見からは、データでは見えない課題や、仕入先との信頼関係や対応力といった強みも把握できます。
たとえば、購買業務においては以下の強み・弱みがあげられます。
| 区分 | 内容 |
| 強み |
|
| 弱み |
|
バリューチェーン分析では、単なるコスト削減にとどまらず「顧客にとっての価値」を軸に評価することが大切です。
競合との比較を通じて、自社ならではの差別化できるポイントを明確にしましょう。
ステップ4.VRIO分析を実施する
VRIOとは、強みとなり得る経営資源や活動を、以下の4つの観点から評価するフレームワークです。
- Value:価値があるか
- Rarity:希少か
- Imitability:模倣が困難か
- Organization:組織的に活用できるか
たとえば、購買業務で発見した強みが他社も容易に真似できる仕組みであれば、長期的な競争優位にはなりません。
一方で、独自の仕入先ネットワークや現場のノウハウのように模倣が難しく、自社の組織で最大限活かせる資源であれば、持続的な優位性につながります。VRIO分析を組み合わせることで、バリューチェーン分析は単なる活動整理にとどまらず、将来的な競争力につながる要因を見極められるでしょう。
バリューチェーンの調達活動を最適化するなら購買管理システム

バリューチェーンでは、「主活動」に注目が集まりがちです。そのため、バリューチェーンの基盤を支える「支援活動」、とくに「調達活動」は見落としやすい領域といえるでしょう。なかでもオフィス消耗品や工具といった間接材の購買は全社にまたがるため、実際には企業全体のコストに影響を及ぼします。各部署で分散して購買が行われることで、無駄な工数やコストがかかってしまうケースも少なくありません。
そのような課題に役立つのが、発注から支払までの一連の流れをシステム上で一元管理して最適化する「購買管理システム」です。
購買管理システムを導入するメリットは、以下の3つです。
- 生産性向上:購買業務の工数を大幅に削減でき、コア業務に集中できる
- コスト削減:集中購買の実現や購買データの活用により、コスト削減が可能になる
- ガバナンス強化:購買プロセスの可視化・標準化によりガバナンス強化につながる
購買管理システムでバリューチェーンの土台である「支援活動」を強化することで、「主活動」を含む企業活動全体の質を向上できます。購買管理システムで実現できる内容については、以下の記事で具体的に解説しています。購買管理に課題を感じている方は、参考にしてみてください。

✓ 関連記事もチェック
購買管理システムとは?便利な機能や導入メリットを解説 >>
購買管理システムの機能やメリット、システムの選び方をご紹介。
間接材の購買管理システムをご検討中の方は、以下の資料もお役立てください。

✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
べんりねっとサービス紹介資料 >>
「べんりねっと」の概要を一つにまとめました。
バリューチェーン向上にむけた「べんりねっと」活用事例

バリューチェーンの向上に購買管理システム「べんりねっと」が役立った3つの事例をご紹介します。
- 発注工数を50%削減した事例
- 発注から会計処理までの時間を65%短縮した事例
- 購買担当者数を16名から2名に削減できた事例
購買管理システムがどのようにバリューチェーンに貢献できるかを知り、導入を検討してみてください。
間接材購買の改善手法や事例については、以下の資料でも詳しく解説しています。

✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
~成功事例から学ぶ~間接材の購買業務 改善手法 >>
間接材購買業務の改善に成功した企業様の事例をご紹介
発注工数を50%削減した事例
食品製造業の「カルビー株式会社」では、べんりねっとで間接材の発注から分析までを効率化することで、大幅な工数削減とコスト最適化を実現しています。
従来は複数の購買システムを併用することで発注や承認のフローが煩雑化し、同じ物品を拠点ごとに異なる価格で調達してしまうなど、管理上のムダが発生していました。
べんりねっと導入後は、購買データをグループ全体で一元管理できるようになり、購買金額の集約によるスケールメリットを活かした価格交渉や標準品の設定が可能になりました。発注工数は約50%削減でき、利用者の6割がコスト削減効果を実感しています。べんりねっとは業務効率の向上と同時に、内部統制の強化や継続的なコスト削減を支える仕組みとして、バリューチェーン全体の競争力向上に貢献します。
本事例については、以下の記事で具体的に解説しているので参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「カルビー株式会社」様 >>
一元管理で業務効率化とコスト削減を実現
発注から会計処理までの時間を65%短縮した事例
医薬品製造業の「太陽ファルマテック株式会社」では、購買システムをべんりねっとに一本化することで、発注から会計処理までのプロセスを大幅に効率化しています。
従来は自社システムや専用ECサイトなど3種類の購買ルートを使い分けており、入力や承認の手間が増大していました。さらに請求書処理に月100件以上対応するなど、購買担当・経理担当双方に負担がかかっていました。
べんりねっと導入後は、サプライヤ連携を活用しながら購買ルートを統一したことで、申請者と購買担当両方の発注作業が簡素化し、業務負担の削減につながっています。購買データの集約によって、請求書払いから支払通知方式への移行も可能になり、確認業務の負担も解消されました。発注から会計処理までのトータル時間は約65%短縮でき、担当者の負担も軽減しています。
購買フローを統一し、購買データも集約できたことで、相見積もりの徹底やボリュームディスカウント交渉といった本格的なコスト削減活動にも着手でき、バリューチェーン全体の効率化と競争力強化に貢献しています。
本事例について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「太陽ファルマテック株式会社」様 >>
購買フローを統一し、会計処理の時間を短縮
購買担当者数を16名から2名に削減できた事例
IT系専門商社の「ソレキア株式会社」では、べんりねっとの導入によって購買業務の効率化とコスト削減、さらにSDGs対応も実現しています。
従来は32社の仕入先を16名の購買担当者が個別に対応しており、調達や支払処理が煩雑化して大きな負担となっていました。
べんりねっと導入後は、仕入先を32社から12社に集約し、ワークフロー機能によって承認から仕訳・支払までを電子化しました。その結果、購買担当者数は16名から2名へと大幅に削減でき、ヒューマンエラーも解消できています。購買業務の効率化によって生まれた人員をコア業務へ再配置することで、生産性の向上にもつながりました。
また、環境配慮商品の優先購買を促進する仕組みを活用することで、ISO14001への対応やSDGsの推進にも貢献しています。
本事例については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「ソレキア株式会社」様 >>
購買先の集約と電子化で購買担当者数を削減
バリューチェーン分析とシステム導入で企業の競争力を高めよう

バリューチェーンは、自社の強みと弱みを可視化し、付加価値を最大化するためのフレームワークです。定義や構造を理解するだけでなく、分析によって具体的な改善点を特定し、主活動のみならず支援活動を含めた全社的な最適化が求められます。
とくに調達・購買領域は、企業全体のコスト構造や業務効率に直結するため、システムを活用した最適化が有効です。
購買管理システム「べんりねっと」を導入すれば、間接材の発注から支払までを一元化し、業務効率化・コスト削減・内部統制強化を同時に実現できます。
まずは現状のバリューチェーンを分析し、改善の優先度が高い領域から取り組み、持続的な競争力強化につなげましょう。